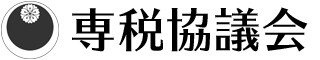『論』 Newest article
インボイス登録申請間に合うのか
(第585号掲載)
インボイス制度開始まで4か月を切った。現在登録申請者数は伸びていないと聞いているが果たして10月1日までで間に合うのだろうか。今後3ヶ月間はまず顧問先の会社の経理が10月1日以降どのように経理処理していく必要があるのか丁寧に説明をしていく必要があり、1社ごとに時間を取っていくものの非常に膨大な時間がかかり途方に暮れている。
コロナ禍で対面することができなかった顧問先とも徐々に対面する機会が増えたため、この時期にインボイス導入後の処理も含めじっくり話をする機会にしたいとも考えている。併せてインボイス導入に伴うチェック時間の増加により顧問報酬の値上げをどうするか考えることも多くなってきて、同業の税理士から顧問契約書の内容変更や値上げの交渉方法などの情報収集も行っていきたいと考えている。
一番頭を悩ませるのは顧問先の取引先へのインボイス番号の取得状況が進んでいないことである。経理体制がしっかりしている企業はいいが、零細企業で経理担当者が一人で回しているところ、外注先が多いところなどは手が回っていない企業が多い。この部分は顧問税理士かしっかりと進捗状況を管理してあげないと結局のところ10月1日以降インボイス番号を取得している外注先とそうでない外注先の区別に時間がかかり、かつ経過措置の処理を行っていくことの説明をしなければならないので、ここでも膨大な時間が説明に取られてしまう。
会計ソフトはすでにインボイス対応が終了しているので入力画面見ると区分記載の個所には100%、80%、50%、控除不可との選択が出てくる。インボイスの説明だけでも大変なのだが経過措置の説明まで含めるとまだ理解できている人は少ないだろう。
その他にも税制改正での1億円以下の会社の1万円未満のインボイス不要などの少額特例、不動産賃貸借契約書やリース契約の改定、スイカなどの電子決済の処理、タクシーの処理など顧問先へ説明しなければならない項目はたくさんある。オフコンメーカーの担当者などは会計事務所を回ってインボイス対応のシステム説明などを丁寧に行ってくれるが、PCソフトやクラウド会計などはホームページを見て自分で勉強してください。というスタンスなので結局税理士事務所は顧問先ごとに自計化先と記帳代行先によってそれぞれ領収書の整理(電子帳簿保存法も含め)から再度説明していかなければならない。
インボイス制度を分かりやすくという小冊子を購入して顧問先に配ろうと思ったが、おそらく熟読してくれる人は少ないだろう。また免税事業者でインボイス制度の説明をYouTubeで見て勉強してくださいと言っても見てくれないだろう。事務所の発行物で1年以上にわたってインボイスのことを説明してきているが、顧問先では「難しそうなので読んでないんですよ。分からないことがあったら都度質問します。」と恐縮するように言われてしまうが、最近やはりインボイスに関しての質問が徐々に増えてきていて、毎度同じ説明を繰り返している。とにかく面倒くさいのである。
最近テレビのCMで電子帳簿保存及びインボイス対応の放映が増えたが、実際にテレビCMを見ている人は少ない。もっと国税はインボイスに対しての周知を政府広報としてテレビCMとして流してもらえないだろうか。もしくは報道機関がニュースでインボイス制度のことについてゴールデンタイムで話してくれないだろうか。あまりにも企業が他人事のように考えていて困ったら税理士が何とかしてくれるだろうと思っている。
不動産の賃借にともなう管理費や修繕積立金、任意の集まりでの懇親会費、毎月の駐車場代、おそらく支払った先がインボイス登録を行っていない(今後も行わないだろう)ところはたくさん存在する。これらの消費税処理は会計データを見ただけでは絶対に確認できず結局全部請求書などの原始帳票に当たらなければならない。これらすべてを税理士事務所がチェックするというのは難しいので結局各顧問先がしっかりとインボイス制度を理解して会計処理を進めていってもらわなければならない。税務調査で税額控除ができなかった際の損害賠償(実際には損害賠償といった大きな話ではなく延滞税と加算税の負担)などの件も事前にお互いで確認しておく必要もある。
居住用不動産の購入に伴う消費税処理や転売不動産の消費税処理、控除対象外消費税の法人税の処理など消費税があるがためにミスが生じた場合には多額の加算税や延滞税が発生する。そもそも消費税処理などはミスにより生ずるものなので誰も間違えたくて間違っているわけではない。消費税に関してはかなりの簡素化を行って欲しいし、税制改正での要望も行って欲しいと思う。
『展望』 Newest article
日本経済動向と消費税増税の因果及びインボイス制度開始への思い
(第575号掲載)
6月2日、米電気自動車大手テスラのCEOイーロン・マスク氏が「経済環境について、とても悪い予感がする」として、新規雇用の中止と人員削減の必要性を幹部社員に示した。翌日の株価急落を受けて、翌々日には撤回するような姿勢を見せたが、同じような考えを持つ経営者は多いだろう。新型コロナやウクライナ侵攻から派生した問題等が絡み合い、世界経済の回復力は低下している。日本もその例外ではなく、小さな負荷が日本経済の思わぬ衰退を招く可能性も考慮すべきだ。
日本経済衰退の歴史は、消費税増税の歴史と重なる。消費税の創設はバブル経済真っただ中であったため負の影響はかき消されたが、バブル経済をハードランディングさせた後、不況下で行われた1997年の5%への増税は、今日まで続くデフレ経済がスタートする契機の一つとなった。2014年の8%への増税では、リーマンショックによる不況以来のマイナス成長(▲0.4%)となり、2019年景気後退局面での10%への増税では、新型コロナウイルスの影響も重なって前回増税時を超えるマイナス成長(▲0.7%)となった。
消費税増税は今の生活を直撃するだけではない。一生涯の可処分所得がその分減るのである。過去に貯めた預金の価値さえ強制的に減ってしまう。理性的な個人は、将来の負担増に対応し、消費を先延ばしする。その行動は褒められこそすれ、責められるところは微塵もない。しかし、その行動が日本経済を停滞させてしまう。個々人の正しい行動が、望まない結果に繋がるのであれば、それはシステムに問題があると言わざるを得ない。
来年10月にはインボイス制度が始まる。既に大企業による免税事業者排除の動きが顕在化しており、やむを得ず課税事業者を選択する中小企業にとっては大きな増税となる。その影響はそこで働く従業者の生活を直撃し、これもまたデフレ不況を深化させる。 繰り返される悪手に対して、政治家が悪い、官僚が悪いというのは簡単だが、問題の原因を他人に帰すると、人は思考停止になる。政治家、官僚、国民がそれぞれの善意に従って努力した結果、今の日本がある。問題は人ではなく、為政者と国民の分断である。国民が為政者に寄り添うべく、投票だけではない、国民の政治参加が重要性を増している。
『寄稿』 Newest article
~機関決定を経る前に、ホームページ、広報誌で方針変更を発表~
日税連理事会傍聴報告 新宿支部 菊池 純
(第576号掲載)
令和4年6月29日シェラトン都ホテルB1「醍醐」で日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)第1回理事会が開催された。
議決事項 一 第66回定期総会提出議案 二 第66回定期総会の招集日時及び場所 三 令和5年度税制改正に関する建議書(案)はすべて賛成多数で可決された。
本報告は、議決事項の「令和5年度税制改正に関する建議書(案)」の重要建議項目中、適格請求書保存方式の導入についてと、それに関連する報告事項 4 インボイス制度の円滑な導入・実施について絞って報告する。
1.方針変更手続きの経過
①日税連ホームページ
日税連は令和4年5月26日ホームページにおいて「インボイス制度の円滑な導入・実施について」を発表、令和3年6月23日公表の令和4年度税制改正に関する建議書で「インボイス方式を見直すとともに、その導入時期を延期すること。」としていた方針を変更した。
突然の発表であり、どこでどのようにして決まったか、何のコメントもない。
②日税連機関紙「税理士界」
日税連の機関紙税理士界(6月15日号№.1413)では、「インボイス制度の円滑な導入・実施に係る提案」として、インボイス制度の実施を踏まえた柔軟な運用に係る、日税連としての提案事項が掲載された。何月何日どこでこのような決定がされたのかはわからないが、日税連ホームページとの関係で、5月26日第2回正副会長会において、と推測する。
この記事によると、同提案は6月2日に開催された自民党税理士制度改革推進議員連盟(会長:宮沢洋一参議院議員、幹事長:西田昌司参議院議員)の第2回インボイス勉強会(発足は昨年11月西田議員の提案による)で報告され、同勉強会には、自民党議員のほか関係省庁の担当官も出席してたとして、出席議員全員が賛意を示し宮沢会長も前向きに検討すると約した旨が書かれ、年末の税制改正大綱に向け要望を強めていくとしている。
③日税連建議書
6月29日第1回日税連理事会において建議書案が審議され、議決された。
建議書の重要な変更点は、令和5年度税制改正に関する建議書(案)の重要建議項目1.に「適格請求書等保存方式の導入時期を延期するか、少なくとも中小企業者の実務を踏まえた柔軟な運用を行うこと。」とされ、前年までの建議書内容に太字部分が加筆された。
また、報告事項の4 インボイス制度の円滑な導入・実施について(令和4年5月26日付)では、これは建議書案に沿って提案したとの説明があった。
2. 批判的見解
建議書案が日税連理事会で可決される前に、建議書に沿った提案を日税連ホームページ及び日税連機関紙で発表した。
さらに、前年の建議書で「見直し、延期」としていた内容を、「円滑な導入・実施」と180度舵を切ったもので、手続きとともに到底承知できない。
各単位会の意見書は税理士会員の意見の結晶である。日税連が何と言おうが各単位会の意見書は生きている筈である。
少なくとも東京会はインボイス制度導入反対の意見を維持している。東京会の公式見解はずっとインボイス制度導入反対である。
税の専門家である税理士は、インボイス制度は導入しなければならない理由が存在しない中で、多くの負担を招くだけの制度を導入すべきでないから反対してきたはずである
インボイス制度の問題点が何も解決しない中、国民のためにならないとわかっていて円滑な導入など提案したら、納税者の権利を擁護するという使命を掲げる税理士会は、納税者からの信頼を失うことになる。
「税界展望」 掲載記事 最新10件
- 2023年08月07日論
- インボイス登録申請間に合うのか
- 2023年08月07日論
- デジタル社会との付き合い方
- 2023年05月26日論
- 印紙税の課税根拠は?
- 2023年05月12日論
- 電子化される税務調査
- 2023年05月12日論
- どうする ! 税務相談
- 2023年02月03日論
- 二転三転するインボイス制度の説明、どうしていますか?
- 2022年12月12日展望
- 日本経済動向と消費税増税の因果及びインボイス制度開始への思い
- 2022年12月09日特別寄稿
- ~機関決定を経る前に、ホームページ、広報誌で方針変更を発表~
- 2022年12月09日論
- 免税事業者への適格請求書発行事業者の登録の説明をどうするか?
- 2022年11月07日特別寄稿
- 税理士法の改正について