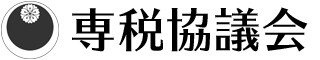『論』 Newest article
今こそ納税者権利憲章を
(第609号掲載)
今年1月に開会した第217回国会において、3月31日に可決成立した「令和7年度の所得税法等の一部を改正する法律案」の衆参両院の付帯決議に、納税者権利憲章に関する規定が盛り込まれました。
十三 税務行政において納税者の権利利益の保護を図り、税務行政に対する国民の信頼醸成や適性を確保するため、納税者権利憲章の策定を含め納税環境整備について検討を行い、その実現に努めること。
2011年1月に時の与党である民主党政権が国会に提出した「所得税法等の一部を改正する法律案」には、納税環境整備の一環として「納税者権利憲章の策定」が盛り込まれていました。
・名称は「納税者権利憲章」とする。
・2011年中に策定し、2012年1月に公表予定。
・国税通則法に納税者の権利利益を図る趣旨を明記するとともに、「納税者権利憲章」の策定を義務付け、
策定根拠、記載内容を定める。
・「納税者権利憲章」は行政文書として国税庁長官が作成・公表する。
・「納税者権利憲章」の内容については凡そ次のとおりとされていた。
納税者の自主的な申告納税を援助する各種サービスを明らかにする。
税務手続きにおける納税者の権利利益を明らかにし、納税者・国税庁の役割を示す。
納税者が処分に不服がある場合の権利救済手続き、税務行政に対する苦情等への対応を明らかにする。
国税庁の使命、税務職員の行動規範を示す。
以上のような提案内容であったが、野党である自民党などの猛反対で納税者権利憲章に関する部分は見送りとされ、この提案は実現しなかった。
納税者権利憲章の必要性は今更指摘するまでもないが、納税者の権利保護法・権利憲章は世界的に社会インフラの一部となっている。このような状況下においては、権利憲章策定の是非は問われるべくもなく、現在の論点は、どのような納税者権利憲章が制定されるべきかであろう。
上記の民主党提案の納税者権利憲章では抽象的な表現であった納税者の権利利益については、以下のように具体的に表記されるべきである。
・税務行政庁から公正で丁重かつ配慮ある対応を受ける権利を有する。
・納税者自ら行った申告について、具体的確証がない限り、真実性・誠実性が推定され、適正なものとして尊重される権利を有する。
・自己の税務情報に関し法律の定める目的以外にその情報を利用されない権利を有する。
・税務調査に際して、事前通知と調査結果の通知を受ける権利を有し、その調査に関し適正な手続きを受ける権利を有する。
・税務処分に対し、不服を申し立てるか、直ちに訴訟を起こす権利を有し、係争中は係争額を納付する義務を負わない。
以上に加えて、今日的な問題として税務行政庁のDX化に伴う権利保障、救済などに配慮した事柄についても盛り込まれなければならない。
いずれにしても衆参両院の付帯決議に納税者権利憲章の策定が盛り込まれたことを好機 として、是非とも納税者権利憲章が制定されるよう願ってやまない。
『展望』 Newest article
専税協議会第57回定期総会

(第586号掲載)
令和5年7月22日(土)午後1時30分より、アルカディア市ヶ谷(私学会館)4階「飛鳥」において、専税協議会第57回定期総会を開催した。
第一部 定期総会、第二部 記念講演、第三部 懇親会を開催し、盛況裡に終了した。
第一部
定期総会は午後1時30分より、青木久直副会長が司会を担当する旨を述べ、全体の流れについて説明をした後、開会の宣言を行った。続いて菅原祥元会長から会員への謝辞とともに、インボイス制度反対についての取り組み等この一年間の活動の報告、12月の東京税理士会役員選挙において、勝又和彦会員が副会長に当選した旨の挨拶があった。
議事に入る前に平野信吾監事より、本日までに専税協議会事務局に届いた議決権行使書について、83名中36名の書面による議決権行使書が届いているとの報告があった。また、現在会場の出席者は9名であると報告された。議長として麻生昌敬会員(江戸川南)が選出され議事に入った。第1号議案から第4号議案まで賛成多数で承認可決され、第5号議案において菅原祥元(麻布)会長をはじめとする新役員が選任された。(新役員の名簿は本誌●Pに掲載)
第二部
記念講演は、阿部徳幸氏(本郷支部/税理士、日本大学法学部・同大学院法学研究科教授)を講師に迎え、「デジタル化に向けて税理士はどうするべきか?」をテーマにご講演頂いた。
第三部
懇親パーティは、部屋を移して盛大に行われ、なつかしい顔合わせ、新しい面々など互いに懇親を深め、有意義なひと時を過ごした。
『寄稿』 Newest article
「まち歩き」の記 ‥‥ その7
(第599号掲載)
渋谷支部 倉林倭男
初冬の澄み切った青天の下、出身校(現小石川中等教育学校)ゆかりの地を巡るまち歩きを実施した。午後2時に旧小石川高校の正門前に集合し、前後30期にわたる同窓生約30人でのまち歩きであった。
まず不忍通りを大塚方面に進み、途中で左折し明化小学校へ。ここは戦時中校舎が被災した時に一時仮住まいした学校である。さらに文京十中、林町小学校を巡る。途中に一橋徳川家所有の樹林園が保存された千石緑地を見学。それから小石川植物園脇の網干坂を下って、占春園へ。ここは江戸時代松平頼元の屋敷の庭であったところで樹木が鬱蒼と茂っている。占春園の脇を抜けると、教育の森公園である。ここは府立五中初代校長の伊藤長七ゆかりの東京高等師範学校(現筑波大)の跡地であり、文京スポーツセンターが併設されている。しばらく休憩の後、春日通を渡ってお茶の水女子大、跡見学園、拓殖大学を見ながら、茗荷谷駅前を通って、文京区立茗台中学校へ着く。戦後小石川高校が移転していた同心町校舎の跡地である。校舎前で記念に集合写真を撮る。それから何かと縁のある竹早高校を横目に、傳通院へと歩く。家康の生母お大の方をここへ葬り、後に堂宇を起こし傳通院となったという。
徳川家ゆかりの女性の墓が多くある。傳通院に縁のある澤蔵司稲荷へ向かう善光寺坂の途中、道路の真ん中にムクノキの老木が枝を伸ばしている。文京区の天然記念物に指定されているそうだ。澤蔵司稲荷にお参りした後に近くのこんにゃく閻魔を見学する。江戸時代、目を患った女性が近くの閻魔さまに、平癒を日々願ったところ、夢の中に閻魔大王が現れ、自らの右目をこの女性に与え、眼病を治癒させた。女性は感謝の印として好物のこんにゃくをお供えしたとの由来の閻魔さまである。
歩き疲れたこともあり、懇親会の時間も迫っていたので、東大赤門見学をスキップして、後楽園駅から本郷三丁目駅まで地下鉄を利用し懇親会場へ向かった。なんと楽だったことか。懇親会場へ着いてみると、既に3人の友人が席に座っていて大笑い。いつものように乾杯から懇親会が始まったのであった。
「税界展望」 掲載記事 最新10件
- 2025年12月08日論
- 今こそ納税者権利憲章を
- 2025年11月17日論
- 令和7年分からの所得税について
- 2025年09月01日論
- いよいよオンライン調査が開始される
- 2025年09月01日論
- 税制が難しくなっている
- 2025年09月01日論
- 税理士法人制度のあり方について
- 2025年05月21日論
- 「日本にも納税者権利憲章の制定を!」
- 2025年05月21日論
- 「103万円の壁」をめぐって
- 2025年03月21日論
- 企業を取り巻く状況について
- 2025年03月21日論
- 税制改正
- 2025年02月10日寄稿コラム
- 「まち歩き」の記 ‥‥ その7