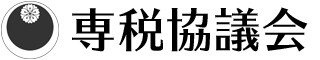税理士紹介ビジネスについての一考察
(第597号掲載)
インターネットの普及に伴い様々なビジネスが誕生した。その一つに代表されるのがマッチングビジネスだろう。税理士業界においても、税理士紹介サイトを営む事業者が誕生して20年超になり、ホームページで検索すると多くのサイトがあり多かれ少なかれその影響を受けていると言える。
税理士紹介サイトについては新たな営業ツールとして注目された一方で悪質な業者により被害を受けた税理士がみられ、また自身の承諾なしに事務所がサイトに掲載されている例もあった。このような状況により税理士法等の解釈または見直しも含め議論となったところである。
日税連が令和4年税理士法改正に際して機関決定した要望書には、会則等で措置する項目として「周旋業者の利用に関する指針の整備」を掲げている。その内容は「日税連・税理士会において納税者の誤導又は誤認のおそれがある誇大広告や比較広告等を禁じている趣旨に鑑み、税理士の品位又は信用を保持するため、税理士の周旋業者の利用に関する指針を設ける」としている。これを受け、日税連綱紀監察部は令和5年4月に「周旋に関する事例集」を公表し会員に対して注意喚起をおこなった。
ここで税理士紹介に関する関連規定を整理してみる。
日税連会則61条(非税理士との提携の禁止)には「法52条又は法第53条第1項若しくは第2項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない。」と規定されている。法52条(税理士業務の制限)、法53条(名称の使用制限)条項は、いわゆるニセ税理士となる者を規定した条項である。つまり、会則上、業務のあっ旋については、にせ税理士からのあっ旋に限定されているため、税理士業務を行っていない税理士紹介業者からのあっ旋については認められることになるとの現行解釈であろう。
では他士業における状況はどうだろう。それぞれの士業を検索してみると、税理士紹介サイトに比べ、極端に士業紹介サービス業者は少ない。
弁護士の場合、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)、法第27条(非弁護士との提携の禁止)、弁護士職務基本規程第11条(非弁護士との提携)、12条(報酬分配の制限)13条(依頼者紹介の対価)等の規定により、紹介ビジネスは弁護士法違反となっている。
司法書士の場合、司法書士倫理第13条(不当誘致等)において「司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。」と規定されており、紹介ビジネスの利用は会則違反になると思われる。
社会保険労務士の場合、税理士法と同様の法体系をとっていると思われるが、茨城県社会保険労務士会HP内のQ&Aには、「他士業の事務所やコンサル会社、サービス会社等が広告、宣伝や営業活動等を行って社労士に業務を依頼したい人を集め、社労士を紹介するような営業代行業務を行うことについては、問題ありますか」との問いに「社労士業務の契約そのものは利用者と社労士が直接締結しているとしても、実質的にサービス会社等が顧客から社労士業務を受託し、その業務を社労士に再委託する形となると思われます。社労士が業務を行って得た報酬の一部が営業代行を行う事業所に入ることや、表面的にはそのようなお金の動きがなくても紹介元が何らかの利益を得ていることも考えられます。たまたま社労士の知人や取引先等から顧客を紹介されるようなケースとは異なり、社労士又は社労士に似た名称を使うなどして顧客を集め、社労士と顧客との間に立って契約の便宜を図ることにより利益を得るような行為は社会保険労務士法により禁止されています。営業代行サービス会社等が営業活動をするにあたって、口頭、書面等で実際に業務を行う社労士や社労士法人の名義を使用することも社会保険労務士法違反となります。
社労士業務に関して社労士以外の事業所が介入するような事業活動は問題となることが多く、注意が必要です。(一部省略)」としている。紹介サービス自体が元請けと下請けの関係になる虞があるとの理論構成により、社労士法違反に抵触する可能性を示唆している。
過度な価格競争による品質の低下や税理士の品位の棄損を惹起しかねない税理士紹介ビジネスについては、今後も危機感を持って注視すべきであり、無償独占である高い公共性のある税理士資格こそ、他士業を参考に法律また会則等での一定措置を検討すべきである。