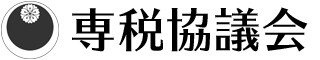税制改正
(第599号掲載)
衆議院議員選挙によって少数与党となった影響で令和7年の税制改正が俄然注目を浴びることとなっている。思い出されるのは民主党政権になった際に法人税の特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度が廃止されたことである。「特殊支配が廃止される」という速報を知り合いの税理士から聞いた際にガッツポーズをした記憶が今でも鮮明に残っている。政権が変わると今まで難しいとされていた税制改正が通ることが実際にあるわけだから、今回103万の壁も改正がされるだろう。
ここで来年以降の令和8年の税制改正に向けては長年の懸案である消費税の改正を本気で訴えていきたいと思う。内容は消費税の税賠訴訟をなくすような改正である。例えば以下のような点である。
- 消費税の簡易課税と原則課税の選択は当該年度の確定申告時に選択が出来ること
- 一括比例配分方式については2年間の強制継続適用をやめること
- 課税売上割合に準ずる割合の事前申請は不要とすること
など手続きの失念(2は除く)などによる損害が発生しないような税制改正を行って欲しいと思う。なお上記のような改正をしたからといって財源問題が大きくのしかかることはないと思う。
上記消費税以外でも日税連の令和7年税制改正に関する建議書で
- 賃上げ促進税制について更正の請求による適用を可能とすること
- 法人税・消費税の申告期限及び納期限を3月以内に改めること。
- 各種届出書及び承認申請書の提出期限の延長をすること
- 準確定申告の申告期限を相続税の申告期限と同様とすること
- 被相続人のインボイスみなし登録期間を、相続税の法定申告期限までとすること。
- 法人版事業承継税制(特例措置)に係る対応期限を延長し、各種届出や申告手続を簡素化すること。
- 法人版及び個人版事業承継税制の特例措置における役員就任及び事業従事要件を緩和 すること。
なども財源問題ではないだろう。(1は影響があると思うが)
上記のような手続き面での改正が通らない理由は何なのだろうか?1つ1つについて「こういった理由から改正ができないのです。」ということが分かるといいと思う。ほとんどの国民にとっては増税か減税かの問題が重要なのであって、手続き面の改正は国民生活に大きく影響はしないだろうし、一方でマスコミもあまり興味を持たないだろう。しかし税理士には税賠により死活問題に発展することがある。来年度以降の日税連・税政連に期待をしたい。
令和7年の税制改正に話を戻すと103万の壁に対して本当の問題は130万の壁であることを専門家はよく分かっているが、あまり論点を難しくすると選挙演説では伝わらないとのことから現在テレビ報道で一生懸命103万、106万、130万の壁の説明をしている。社会保険料の負担のほうが圧倒的に大きいのだからこの問題を根本的に解決しないと結局働き控えはなくならない。第3号被保険者制度は昭和61年4月から開始されたようであり、現在第3号被保険者制度は縮小の方向に向かっている。今後は103万の壁と同時に議論が活発化し働き控えがなくなるような制度設計になることを期待したい。