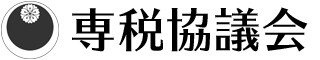企業を取り巻く状況について
(第601号掲載)
中小企業の業績は、業種によってばらつきはあるが、新型ロナウイルス感染症が5種に移行した後、コロナ禍の落ち込みから回復してきていると思われる。
(1)「人手不足」「生産性の向上」
現在多くの中小企業の経営者は人材不足に直面しており、又賃上げにも対応しなげればならない。この「人手不足」を補うため・人件費を捻出するためにも「生産性の向上」を目指す必要がある。
「人手不足」については、働き方改革に基づく時間外労働の上限規制により以前のように少数人数による働き方は難しくなり人手が必要となる。企業における人手不足はますます深刻化している。人材を十分確保できている企業が取組んでいる事項は、①賃金賞与の引き上げ②働きやすい職場環境の整備③定年延長や高齢者・外国人労働者の活用④機械化や自動化の実施等がある。企業の経営者もこれらを真剣に検討する必要に迫られている。
①の賃上げについて、東京都の令和6年の最低賃金は、過去最大50円の引上げの1,163円となった。賃金上昇→消費の増加→製品需要の増加→労働需要の増加→生産性の向上増加→企業収益の増加の成長と分配の好循環を目標としている。しかし物価上昇などの影響による防衛的賃上げ(離職防止などのために行う賃上げ)を実施している企業が多いのが現状である。厚生労働省や経済産業省等における賃上げ支援施策(各種給付金・助成金)により賃上げ環境の整備に向けた取組をしているが、その周知不足もあり活用は少ないようだ。
「生産性の向上」については、①人間が行う作業を見直して効率化を図り、機械やシステムを導入することで作業負担の減少させるための省力化投資を行う。省力化・デジタル化投資の推進による生産性の向上をした企業の売上高はプラスの変化がみられる傾向があるという。
②価格転嫁-従来の低コスト化・数量増加で取組んできた企業もコスト増加分を十分に価格転嫁するように取引先との交渉をする必要がある。経済産業省は中小企業等に対して、2024年4月から9月末の期間に発注企業との間の価格交渉・転嫁の状況を問うアンケート調査を実施。その結果実際に価格交渉を行ったことにより価格に反映された例も最近増加しているとの事。但し原材料・エネルギー費の増加による価格転嫁交渉に比べ労務費増加による価格転嫁交渉は依然として低迷傾向にあるようだ。また価格転嫁率は1次請け企業に比べ4次請け以上の階層の転嫁率は低い。今後の対応として中小・小規模事業者の賃上げ原資確保のためにも価格転嫁対策を継続するとなっている。
(2)小規模事業者の現状
最低賃金は毎年アップするが、製造業等については従来からの受注単価がなかなか変えることができない。また下請け企業では大手企業への交渉は厳しいのが現状である。働き方改革で従業員の労働時間を守るため経営者側がかなりの負担を強いられている。業務改善助成金・キャリアアップ助成金等の各種支援策を実施しているが、周知不足もあり認知度が上がっていない。また利用しようとしても申請等の手続が煩雑で、結局申請を途中で諦めてしまう傾向がある。このような現状を行政は把握して各種施策を実行する必要がある。
(3)その他
①令和7年度税制改正大綱概要に対する対応(内容は税界展望第600号参照)
②企業経営者においては上記①のほか2025年は、行政手続の電子化や育児・介護支援、高齢者・障害者雇用などの分野で法改正が行われる予定。
③職場におけるパワハラ・セクハラ・マタハラ等のハラスメントは法令により一定の防止措置を講ずることが会社に義務付けられている。また2024年11月1日からはフリーランスに対するハラスメントについても防止措置を講じることが義務付けられた。
④お客様からの苦情に対する「苦情対応マニュアル」の作成。最近はカスタマーハラスメントに対する会社の対応を検討し、従業員を守る姿勢を示す。
私たち税理士は顧問先との間において、税務相談以外の事項についての相談にどのような対応をすべきであろうか。