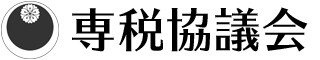令和7年分からの所得税について
(第607号掲載)
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」「給与所得控除」見直し 「特定親族特別控除」の創設が行なわれた。11月までの給与計算については変更なし、改正は令和7年12月1日に施行され令和7年分以後の所得税について適用される。12月に行う年末調整等の源泉徴収事務に変更が生じる。
1.改正の概要
①基礎控除…合計所得金額に応じて基礎控除額が改正された。
令和7年・8年分 合計所得金額132万円以下95万円 令和9年分95万円
132万円超336万円以下88万円 58万円
336万円超489万円以下68万円 58万円
489万円超655万円以下63万円 58万円
655万円超2350万円以下58万円 58万円
合計所得金額2350万円超は基礎控除の改正は無し。
②基礎控除…給与所得について55万円の最低保証が65万円。給与の収入金額190万円以下65万円、190万円超については改正なし。
③特定親族特別控除…居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者・白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族を有する場合は、特定親族1人についてその者の合計所得金額に応じて3万円から63万円の金額を控除する。特定親族の合計所得金額が58万円以下の場合は特定親族特別控除の対象とはならないが、従来の特定扶養親族に該当するため扶養控除63万円の適用はある。
④扶養親族等の所得要件…基礎控除改正に伴い扶養控除の対象となる扶養親族等の所得要件が改正された。扶養親族58万円以下・配偶者特別控除の対象となる配偶者58万円超133万円以下・勤労学生85万円以下となる。
2.令和7年分の年末調整について
①12月から上記の改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有する者は、「扶養控除等(異動)申告書」を給与支払者に提出が必要となる。
②特定親族を有する場合は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与支払者に提出が必要となる。
③従来の「基礎控除申告書」「配偶者控除等の申告書」の所得要件等の改正の改正による確認作業が必要となる。
④改正により給与所得控除後の給与等の金額が改正となっている。
令和7年度の税制改正による所得税改正が12月1日施行であり、令和7年分以降の所得税について適用される。給与支払者は12月の年末調整事務で処理しなければならない。改正内容を正確に把握し、従業員に通知し、資料及び各種申告書の提出を求め年末調整を行う事務負担は大変なものである。給与ソフトが税額計算をするとしても正確な情報を入力しなければならない。個人事業者は令和7年分の所得税の確定申告の際、改正点に注意して申告する必要がある。
このようは複雑な税制改正について、国税庁は「所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイト」開設・パンフレット・よくある質問Q&Aにより周知・広報に努めているとしている。また年末調整手続の電子化の促進として、マイナーポータル連携・国税庁ホームページ内に特集ページを設け周知・広報を図るとしているが、十分とは言えない。
日税連は、年末調整手続の電子化の促進について、「年末調整手続の電子化は、年末調整関係書類の確認事務が 削減され、事業者・従業員双方の業務の効率化に寄与するものです。 本会としても、引き続き、年末調整の電子化推進に向けて税理士会 会員及び納税者に周知・広報してまいります」としている。
私たち税理士は、関与先に改正点・税務処理における注意点を丁寧に説明し、正確な処理ができるようにサポートしなければならない。税務行政のDXは今後とも急速に実施されるとおもわれるが、デジタルについていけない事業者・納税者がいることも忘れてはならない。