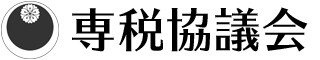いよいよオンライン調査が開始される
(第606号掲載)
令和7年9月から税務調査がオンライン化され、法人・個人事業主を含む全納税者、および全税目(法人税・消費税・所得税・相続税・贈与税など)を対象に段階的にスタートする。
オンライン調査で導入される主な仕組みはマイクロソフトのTeamsを利用するようなのだが、Zoomではセキュリティーの問題があるのだろう。連絡はメールが中心になるようで調査の事前通知は引き続き電話等で実施されるが、資料準備の依頼などはメール連絡が主になるようだ。そして資料提出についてはクラウド経由で提出できe-Taxの併用も可能であるようだ。実際の導入スケジュールについては令和7年9月から金沢国税局および福岡国税局とその管内の税務署で先行スタートし、令和8年3月から6月にかけて、他の国税局・税務署にも順次展開予定とのことだそうで、いよいよオンライン調査が開始となる。
まず金沢国税局と福岡国税局管内でオンライン調査が開始されたら、どのような調査が行われたのかの情報提供がされると思うのでオンライン調査に対する準備もできていくと思うが、報道によるとオンライン調査と対面調査は選択できる模様である。
筆者はコロナ禍に相続の調査を対面ではなく電話と資料提出で行った経験があるのだが、その時の流れは、調査官からどこが調べたいのかを事前に書面で提出され、その質問に対して回答するという流れだったので非常に短期間(短時間)で終了することができた。顧問税理士は被調査会社のどこを調査したいのか事前に分かっているケースもあるだろうから、論点だけをお互いに議論すれば済む調査であれば非常に短期間で終了することができお互いにとって効率的であろう。
実際のところオンライン調査に関しては次のような疑問がわく。税理士もしくはお客様はオンラインと対面のどちらを選択するだろうか。お客様は税理士に任せるだろうがそれぞれにメリットデメリットがあるだろう。オンラインのメリットは時間の節約である。若い調査官などで総勘定元帳だけをずっと見続けているケースがあるが、そんな調査手法では何も分からないだろうし、時間つぶしをしているとしか思えない。このような調査であるならばオンライン調査で論点だけを質問されたほうが効率的である。また納税者の会社や自宅に臨場しないので雰囲気が分からないというところもメリットかもしれない。特に相続の調査などは被相続人の自宅へ行くことなく調査が進むので相続人の負担も少ないだろう。
一方でデメリットは総勘定元帳を電子データで送ることになるとチェックされる時間が多くなるために納税者にとって不利になってしまう可能性があることだ。通常の対面調査では総勘定元帳から請求書・領収書にあたるので、オンライン調査でも請求書や領収書をすべて送ることは要望されないだろう。総勘定元帳をチェックしたうえで送ってほしい請求書や領収書の依頼があると思われる。
今年の春の調査では2年目の調査官が事前に総勘定元帳を電子データで送ってほしいという旨の依頼があったがもちろんお断りをした。「なぜそのような要求をするのか?」と尋ねると「調査を効率的に進められるから」との理由だったのだが、事前に総勘定元帳のデータを送ることがどれだけ被調査会社のデメリットになるかは調査官は分からないのだろう。あくまでも時間効率を考えているだけのようであった。その一方で相続の場合には総勘定元帳は存在しないので、通帳の写しなどを事前に送ることで要は足りるので、やはりオンライン調査のほうがメリットがあるだろう。
次にTeamsでオンライン調査を行っている際にレコーディングされる(もちろんこちらがレコーディングすることもあるが)のであろうか。税務調査は隠れて録音するということが言った言わない論争で負けない方法でもあると研修で習ったことがあるが、オンラインであれば録画ができるため、後の事務所の研修材料に使うことができる。当然守秘義務の観点から第3者への研修には使えないが、仮に法廷で争うことになる場合には、弁護士に録画を見せることはあるだろう。
調査選定には今後AIが導入される。AIが選定する以上、選定されないにはどうすればいいかを研究すればよい。調査を受けないことが一番であるが、ケースによってはオンライン調査を選択してみるのもいいかもしれない。