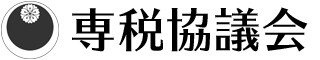税制が難しくなっている
(第605号掲載)
皆さんもご存じのとおり、税金を広く公平に分かち合っていくための基本原則として税の三原則があります。「公平、中立、簡素」が税制構築の基本原則となっています。
「公平」の原則は、それぞれの担税力(支払能力)に応じた負担を求める考え方であり。「水平的公平」と「垂直的公平」があります。「水平的公平」とは、同じ所得や資産を持つなど等しい負担能力のある人は等しく同じ税負担を求めることです。「垂直的公平」とは、所得や資産が多い人には、より多くの税の負担を求めることです。
「中立」の原則は、税制が経済活動の選択を歪めないようにすること。たとえば、法人事業か個人事業かの違いで税の負担が大きく変わると経済的合理性でものごとが判断されるのではなく、税制上の有利・不利で行動が決まってしまうので中立性を保つことが重要です。
「簡素」の原則は、税制の仕組みをえきるだけ簡素にし、分かりやすく、運用しやすくすること。そして納税者が自分の税負担を理解しやすいものにすることです。
昨年の6月から始まった定額減税は手間がかかりましたね。思い出してみると所得税から3万円、住民税から1万円が控除されました。家族構成によって減税額が変わりますし、本人の合計所得金額によって制限もあります。所得税について、給与所得者は源泉徴収税額から控除され、個人事業者は本人に係る分については予定納税から控除されました。事前の準備でもいろいろと資料を用意しました。
また、令和7年の税制改正では、103万円の壁が123万円へと引き上げられました。
内容としては、一つ目が、基礎控除額について、これまでは合計所得金額2400万円以下の方は48万円が控除され、2400万円を超え2500万円以下の方は金額が増加するごとに48万円の基礎控除額が段階的に逓減し、2500万円を超えると基礎控除がゼロとなる制度でした。改正では、この基礎控除額が合計所得金額が2350万円以下の方については58万円に引き上げられます。それと、令和7年と令和8年について、合計所得金額が655万円以下の方について基礎控除額が段階的に63万円から95万円の間で引き上げられます。
二つ目が、給与所得者の給与所得控除額が令和6年までは55万円の控除でしたが、令和7年からは給与所得控除額が65万円に引き上げられました。
そのほかにも、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正等々が所得税の改正としてあります。
税制改正がこのまま進んだら複雑化するばかりで、一向に税の三原則である簡素化に向かうことは無いように思えてしまします。
税制が複雑化する背景には、いくつかの理由があると思います。じつは社会や経済の変化が複雑に絡み合って、調整されながら作られているからと思います。
その理由をAIに聞いてみますと
税制が複雑になるのには、いくつかの根深い理由があります。
1.歴史的な積み重ね
法律が改正されるたびに、新しい条項が追加されるが、古いものは完全に廃止されずに残ることが多いです。「例外の例外」や「特例の特例」が増えていき、結果として全体の構造が難解になります。
2.公平性と配慮のバランス
低所得者や中小企業、特定の産業・地域への配慮を反映しようとすると、特例措置が必要になります。公平性を保つために複雑な控除や免税、還付制度が導入されがちです。
3.政治的な要因
利害関係の調整の中で、「誰も損をしない」形を模索すると、単純化よりも調整的な制度になります。税制改革は票に関わるため、広範な改正よりも細かい変更が優先されがちです。
4.経済や社会の変化への対応
グローバル化やデジタル経済の進展に伴い、所得や資産の種類も複雑化。
個人と企業の多様化した働き方・資金の流れに対応する必要があるため、仕組みも複雑になります。
以上がAIの回答でした。
いっそのこと、税制改正もAIに任せてみては、いかがでしょうか。
しかしながら、AIは過去のビックデータから学習してきますので補佐的な業務は得意でしょうが、理論的な判断は難しいようです。やはり人間がしっかりと作成しないといけませんね。