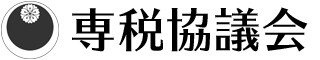税理士法人制度のあり方について
(第604号掲載)
平成13年税理士法改正(平成14年4月1日施行)により、税理士法人の設立が可能となった。従来までは、税理士業務については、昭和26年の税理士法制定以来、資格を与えられている一身専属たる個人(税理士)が、その責任において行うべきものであり、有資格者たる自然人以外は行うべきではないとされてきた。
しかし、我が国の社会経済の進展に伴い、企業を取り巻く経営環境はますます複雑化、高度化、国際化してきた状況において、税理士はその複雑かつ高度なニーズに応えるためには、税理士業務の共同化がきわめて有効であるとの意見が高まってきた。
こうしたなかで、当時の政策の流れとなる規制緩和推進3ケ年計画の要請も受ける形で、税理士による多角的で継続的な業務提供や賠償責任能力の強化等を通して業務への信頼性を高めるとの観点より税理士法人制度が創設されることになった。
その後、税理士法人制度は徐々に業界において浸透し、税理士法人届出数は主たる事務所が5,146事務所となり、従たる事務所は2,935事務所となっている。また、税理士登録者81,696名のうち社員税理士数は13,734名、税理士法人に所属する税理士数は6,640名となり、約25%の税理士が税理士法人に属することになっている(令和7年3月現在)。
税理士法人制度がスタートして20年超が経過し、近年、会員間において議論に挙がるのが「社員の責任」と「一人税理士法人」であろう。
「社員の責任」に関しては結局、無限連帯責任が採用されたわけであるが、平成13年当時税理士会においても「無限連帯責任論」と「一部有限責任論」とで二分する意見があったようである。
一部有限責任を導入すべきとした主な意見は「①監査法人についても有限責任制の導入が検討されており、また弁護士法人においても有限責任を加味した在り方とすることを視野に入れて検討されている」「②一部有限責任を導入しても現在の自然人たる税理士の責任負担に加え、法人の財産も責任対象となることから納税者への責任はより強化できる」「③国際化の流れを考えれば、アメリカなどの諸外国では専門職法人は有限責任が主流である」などであった。
一方、無限連帯責任を導入すべきとした主な意見は「①税理士法人が基本的には合名会社法制を基礎としており、個人色の強いもの(税理士の集合体)と考えるならば、あるいは納税者の有利性を考えるならば全社員の無限連帯責任とすべきである」「②税理士の公共的使命から考えて、納税者に対する責任は重くあるべきである」「③業務の性格上、法人の資産は乏しいと考えられることから、一部有限責任ではかえって納税者保護の強化につながらない」「④税理士相互がお互いに業務を組織的に監視することが可能となり、税理士業務の執行の誤りなどについての事前抑止が可能となる」「⑤無限連帯責任制を導入すれば、巨大な税理士法人の出現や従たる事務所の拡散について抑制の機能が働く。」などであった。
税理士法人制度が誕生し20年超が経ち、当時の税理士会が想定していた未来とは違った環境になっていることであろう。「社員の責任」の在り方について会員間でも意見が分かれるところであろうかと思うが、これだけ多くの会員が法人に従事していることを踏まえれば、次期税理士法改正の際に検証を進めるべきではないかと思う。
もう一点の議論となっているのが「一人税理士法人」である。この議論においてもやはり会員間では意見が分かれることになろう。
将来の税理士制度を考えるうえで、納税者保護の観点は当然に必要になるわけであるが、一方で、私たち税理士が業務をしやすくなるような環境を作っていくことも大事な視点となる。このバランスをどのような形で保ち、制度設計を行っていくべきなのか。税理士法人制度については、他士業の制度も参考に再考すべき時期が来ているのではないかと感じる。